古今和歌集 巻二:春下 111~120首の魅力

*この画像はイメージです
『古今和歌集』巻二「春下」に収められた111首から120首は、春の風情や儚さ、そして自然と人の心の交わりを詠んだ優れた和歌が揃っています。これらの和歌は、春の景色や花の散る様子を描写しつつ、それぞれの詠み人の心情を繊細に映し出しています。
here、それぞれの和歌の作者(読人知らずを含む)、原文、ローマ字読み、meaning、background、そして翻訳では伝わらない日本語の良さを詳しく解説します。
第111首 読人知らず
原文
こまなめて いざ見にゆかむ ふるさとは 雪とのみこそ 花はちるらめ
ローマ字読み
Komana mete iza mi ni yukan furusato wa yuki to nomi koso hana wa chirurame

*この画像はイメージです
meaning
馬を連ねて、故郷に立ち寄ってみようではないか。そこでは花は雪のように散っていることだろう。
background
春の花見に向かいながら、今頃は桜の花が雪のように散っているだろうと、そんな光景に期待を膨らませながら詠んだ歌です。「雪とのみこそ」という表現が、散る花びらと雪を重ねている点が美しい。
Good things that cannot be conveyed in translation
「こまなめて」という言葉には、馬を駆って勢いよく進む様子が含まれます。日本語特有の擬態語の豊かさがここにあります。
第112首 読人知らず
原文
ちる花を なにかうらみむ 世の中に わが身もともに あらむものかは
ローマ字読み
Chiru hana wo nani ka uramimu yo no naka ni waga mi mo tomo ni aramu mono ka wa

*この画像はイメージです
meaning
散る花をどうして恨むことがあろうか。この世に生きる私もまた、やがては散る運命なのだから。
background
桜が散る様子を、人の命のはかなさに重ねています。仏教的な無常観がにじむ一首です。
Good things that cannot be conveyed in translation
「なにかうらみむ」という表現が、単なる疑問ではなく、人生観としての悟りを含んでいる点が日本語の繊細な表現力を示しています。
第113首 小野小町(おののこまち)
原文
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
ローマ字読み
Hana no iro wa utsuri ni kerina itazura ni waga mi yo ni furu nagame seshi ma ni

*この画像はイメージです
meaning
花の色は色あせてしまった。ただむなしく、私の身もまた、長い年月を憂いながら過ごしているうちに老いてしまった。
background
日本の美の象徴である桜の花と、女性の若さや美しさを重ねた名歌。小野小町の歌の中でも特に有名です。
Good things that cannot be conveyed in translation
「ながめ」には「眺める」と「物思いにふける」の二重の意味があるため、英語に訳すとその深みが失われがちです。
第114首 素性(そせい)
原文
をしと思ふ 心はいとに よられなむ ちる花ごとに ぬきてとどめむ
ローマ字読み
Oshi to omou kokoro wa ito ni yorarenamu chiru hana goto ni nukite todomemu

*画像はイメージです
meaning
惜しいと思うこの心を、糸に通すことができたならば、散る花を糸で縫い留めてしまいたい。
background
花が散ることを惜しみ、その儚さを止めることができないもどかしさを、具体的な糸に結び付けることで美しい比喩で表現しています。
Good things that cannot be conveyed in translation
「ぬきてとどめむ」という表現が、日本語独特の情緒的な比喩を持つ点が重要です。
第115首 紀貫之(きのつらゆき)
原文
あづさゆみ はるの山辺を こえくれば 道もさりあへず 花ぞちりける
ローマ字読み
Adusayumi haru no yamabe o koekureba michi mo sari ahezu hana zo chirikeru

*この画像はイメージです
meaning
春の山道を越えてくると、道さえ整わぬまま、花がすでに散っていた。
background
志賀の山越えの際に、大勢の女性と会ったときに詠んだものです。狭い山道で出会った美しい衣装の女性たちを、折から散る花に例えています。
Good things that cannot be conveyed in translation
「さりあへず」は、「整う」や「間に合う」の意味を含み、旅路の厳しさと花(女性)の儚さを同時に表現しています。Also、あづさゆみは「はる」に掛かる枕詞であり、「張る」と「春」の意味をかけたものでもあります。
第116首 紀貫之(きのつらゆき)
原文
春の野に 若菜摘まむと 来しものを 散りかふ花に 道はまどひぬ
ローマ字読み
Haru no no ni wakana tsumamu to koshi mono o chiri kau hana ni michi wa madoinu

*画像はイメージです
meaning
春の野に若菜を摘もうとやってきたが、舞い散る花に道に迷ってしまったようだ。
background
春の風景を楽しもうとしたものの、桜の花が舞い散る中で、視界が遮られ道に迷ってしまう程の様子が描かれています。
Good things that cannot be conveyed in translation
「道はまとひぬ」は、花が散ることで進むべき道が見えなくなるという比喩的な表現です。
第117首 紀貫之(きのつらゆき)
原文
やどりして 春の山辺に ねたる夜は 夢のうちにも 花ぞちりける
ローマ字読み
Yadori shite haru no yamabe ni netaru yo wa yume no uchi ni mo hana zo chirikeru

*この画像はイメージです
meaning
春の山で宿を取り、眠った夜には、夢の中でさえ花が散っていた。
background
山寺に参詣したときに詠んだもので、昼間に見た春の花の美しさと儚さを、現実と夢の両方で感じている情景を描写しています。
Good things that cannot be conveyed in translation
「夢のうちにも花ぞちりける」という表現が、現実と幻想の境界を曖昧にし、日本的な情緒を醸し出しています。
第118首 紀貫之(きのつらゆき)
原文
吹く風と 谷の水とし なかりせば み山かくれの 花を見ましや
ローマ字読み
Fuku kaze to tani no mizu to shi nakariseba miyama kakure no hana o mimashi ya

*この画像はイメージです
meaning
吹く風と谷の流れる水がなければ、深い山奥に隠れた花を見ることができただろうか。
background
自然の要素によって花が散ってしまうが、それがなければその美しさにも気づかなかったことを示唆しています。
Good things that cannot be conveyed in translation
「み山かくれの花」は、奥深い場所にひっそり咲く花のことを指し、日本独特の秘められた美を表しています。
第119首 遍昭(へんじょう)
原文
よそに見て 帰らむ人に ふぢの花は 這ひまつはれよ 枝は折るとも
ローマ字読み
Yoso ni mite kaeramu hito ni fuji no hana wa hai matsuware yo eda wa oru tomo

*画像はイメージです
meaning
藤の花よ、よそよそしく花だけ見て帰る者に、絡みついて引き止めよ。枝が折れてしまっても。
background
志賀からやってきた女性客が、お寺に入っても藤の花だけ見て帰ってしまった事に対して詠んだものです。住職に挨拶もなしに帰ってしまう女性たちに対して、呆れているような趣旨が読み取れます。
Good things that cannot be conveyed in translation
「這ひまつはれよ」という表現が、藤のつるの絡みつく様子を生き生きと描いています。
第120首 躬恒(みつね)
原文
わがやどに 咲ける藤波 立ちかへり 透きがてにのみ 人の見るらむ
ローマ字読み
Waga yado ni sakeru fujinami tachikaeri sugi gate ni nomi hito no miruramu

*この画像はイメージです
meaning
我が家に咲く藤の花を見て、人々が引き返してもう一度見ようとしているようだ。
background
藤の花の美しさが、訪れる人々を魅了する様子を詠んでいます。趣向を凝らさずにありのままを詠んでいることから、余程素晴らしい花だという事が分かります。
Good things that cannot be conveyed in translation
「透きかてにのみ」という表現が、藤の花の繊細で優雅な美しさを巧みに描いています。
summary

*この画像はイメージです
『古今和歌集』の春の和歌には、ただ美しい景色を詠むだけでなく、人の心情や人生観が込められています。桜の散る儚さを人生の無常と重ねる表現、擬態語や掛詞による繊細な言葉遊びなど、日本語ならではの豊かな表現が光ります。
翻訳では伝えきれない微妙なニュアンスや、言葉の響きの美しさを味わうことで、和歌の魅力をより深く感じることができるでしょう。




![[World's Insanity] Japan's choice for married couples to have the same surname - Is it a culture?、Is it bondage?](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2024/11/wedding-name.jpg)

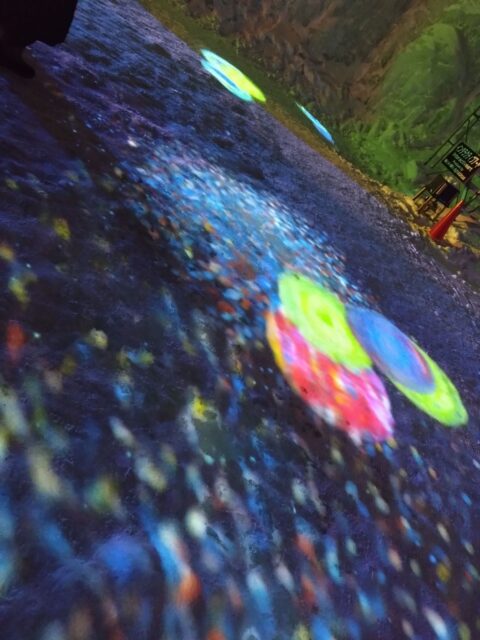
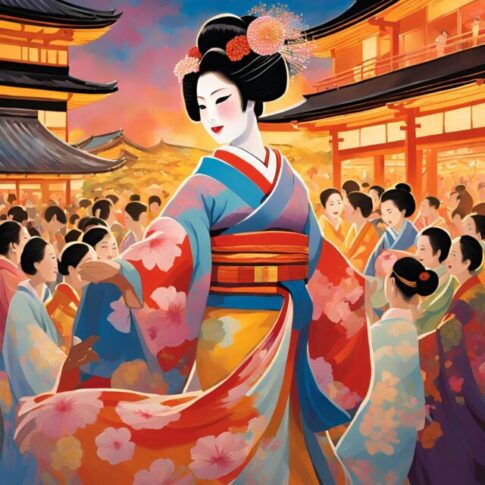









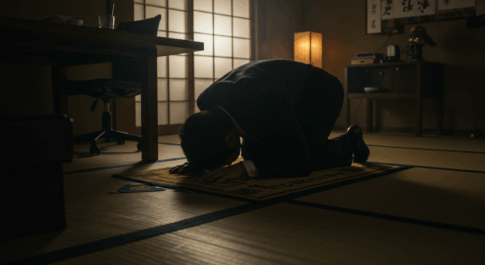











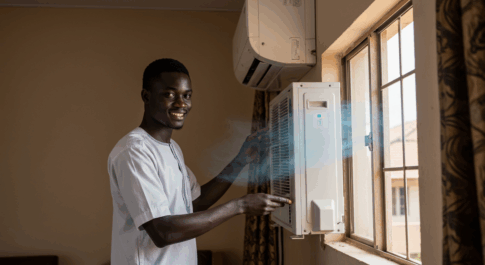





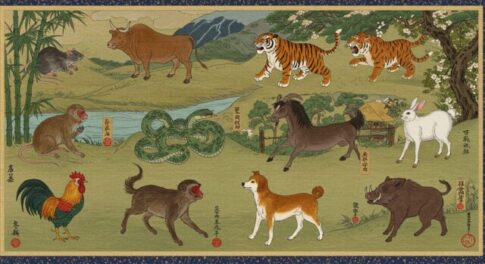
Leave a Reply