「日本のお笑いって、こんなに面白いんだ!」
そんな驚きの声が、最近になって海外から聞こえてくるようになりました。
アニメや食文化、伝統芸能に続いて、いま静かに注目を集めているのが“笑い”の力。
言葉も文化も異なるはずの場所で、日本の芸人たちが笑いを巻き起こし、拍手喝采を浴びる瞬間が増えているのです。
今回は、そんな“国境を越えた笑い”を体現した日本の芸人たちに焦点を当て、なぜ彼らのユーモアが海外に届いたのか、どんな表現が世界で受け入れられているのかを紐解いていきます。
海外で火がついた、日本の芸人たちの挑戦
世界が踊った“PPAP” ─ ピコ太郎の超短尺ギャグ

まず紹介したいのは、2016年に突如世界的ブームを巻き起こした「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」。
金色の派手な衣装、意味不明とも言える歌詞、そして絶妙なリズム感。そのすべてが“妙にクセになる”と評判を呼び、YouTubeでは2億回以上再生されました。
この爆発的ヒットを後押ししたのは、あのジャスティン・ビーバー。「今一番好きな動画」として紹介したことで、一気に世界中の注目を集め、CNNやBBCなどの国際ニュースでも特集が組まれるほどに。
意味よりノリ、言語よりテンポ――そのユニークさが、世界中の笑いのツボに刺さったのです。
身体で笑わせる男 ─ ウエスP(Mr. Uekusa)

日本では“裸芸人”として知られるウエスPは、物理ギャグとタイミング芸を融合させた独自のスタイルで海外にもファンを増やしました。
とくに注目されたのは、テーブルクロス引きと巧妙な裸芸を組み合わせたパフォーマンス。これが世界的オーディション番組『Got Talent』シリーズで絶賛され、SNSでも数千万回再生されるなどの大反響を呼びました。
彼のネタには言葉が一切不要。だからこそ、TikTokやInstagramでも世界中の視聴者に刺さりやすく、1000万人以上のフォロワーを獲得しました。まさに、視覚と間で魅せる「ノンバーバル・コメディ(非言語的な笑い)」の強みが発揮された成功例です。
英国を笑わせた「安心してください」 ─ とにかく明るい安村

2023年には、とにかく明るい安村がイギリスの人気番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』に出演し、日本でも知られる「安心してください、穿いてますよ」という裸芸を英語バージョンで披露しました。
初めて見る人にとってはシュールきわまりないその芸に、最初は戸惑いもあったようですが、次第に会場は大爆笑。
辛口で知られる審査員サイモン・コーウェルをも笑わせ、セミファイナルまで進出。長年日本で磨かれた“間”と“表情”が、見事に海外でも通用した稀有なケースでした。
日本のお笑いが海外で伝わりづらい理由

一方で、日本のお笑いが海外で普遍的に通用しているわけではありません。そこには、いくつかの文化的・言語的なハードルがあります。
日本の漫才やコントは、「ボケ」と「ツッコミ」による高速のやり取り、言葉遊び、方言やイントネーションといった“言語依存度”が非常に高い構造になっています。また、日常の微細な違和感や人間関係に根ざしたネタも多く、文化的な共有経験がなければ理解されにくいという問題があります。
欧米のスタンダップコメディのように、社会問題や時事ネタ、アイロニーを通じた批判精神が重視される笑いとは、性質そのものが異なるのです。
“言葉の壁”を超えるカギは「ノンバーバル」

そんな中で注目されているのが、言葉をほとんど必要としない「ノンバーバル・コメディ」です。
表情、動き、間、音楽といった非言語的要素で構成されるパフォーマンスは、字幕も翻訳も必要なく、誰にでも“直感的に”面白さが伝わります。
ピコ太郎、ウエスP、安村といった芸人たちは、まさにこのスタイルを駆使して、SNSや動画配信を通じて国境を越えてきました。
また、短尺でテンポよく完結する形式は、TikTokやYouTube Shortsといった“ショート動画”時代のニーズとも合致しており、「一発で笑わせる」構成力がますます重視されるようになっています。
これからの“世界基準の笑い”に必要なこと

これから日本のお笑いが本格的に世界へと羽ばたいていくには、いくつかの課題と可能性があります。
まず求められるのは、多様性に開かれた視点。ジェンダー、宗教、人種といったセンシティブな話題への配慮はもちろん、文化を越えて誰もが安心して笑える“ユニバーサルなネタづくり”が求められます。
さらに、演出面でも映像表現や音響効果を活かし、グローバル視聴者に「伝わる」工夫が欠かせません。今や“笑い”は舞台だけでなく、SNS上でも演じられ、シェアされるもの。舞台芸人から動画クリエイターへと変身できる柔軟性こそが、次の時代の武器になるかもしれません。
まとめ:笑いは、言語よりも早く心に届く

笑いは、人種も国籍も関係なく、人と人をつなぐ力を持っています。だからこそ、言葉が通じなくても、価値観が違っても、思わず吹き出してしまう瞬間は生まれるのです。
ピコ太郎のリズム、ウエスPの動き、とにかく明るい安村の間と表情――彼らが世界に見せたのは、日本の笑いが“翻訳を必要としない芸術”にもなり得るという希望でした。
世界中が同じ動画を見て、同じように笑うその光景こそ、まさにボーダーレスな時代の象徴です。
これからも、国境を越えて人々を笑顔にする日本のお笑いに期待しましょう。
もしこの記事が面白かった、役に立ったと感じたら、ぜひコメントで感想を教えてください。
SNSでのシェアや、ブックマークも大歓迎です。
あなたの一言が、次の“世界に届く笑い”をつくるヒントになるかもしれません。
私、長野真琴はこれからも日本の素晴らしいエンタメ文化を世界に発信していきます。それでは、また次回の記事でお会いしましょう!




![[名馬列伝シリーズ 初回]異次元の逃亡者 サイレンススズカ―競走馬人生を駆け抜けた涙の結末](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/02/image_fx_-2025-02-25T104924.322-485x264.jpg)
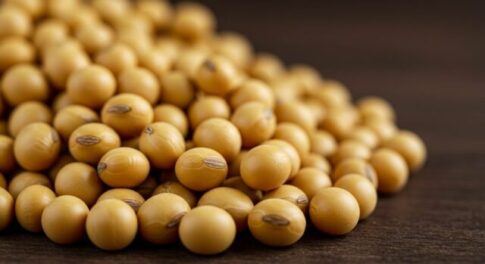

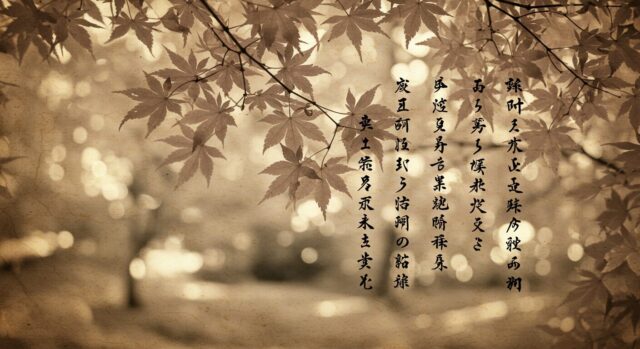

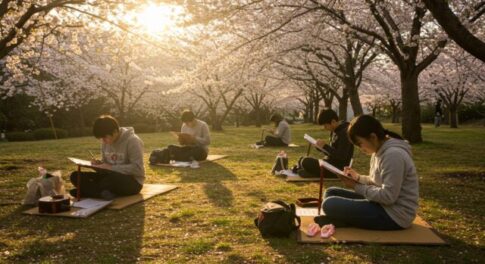








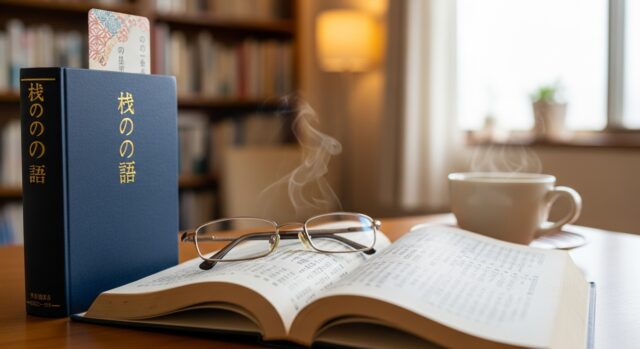



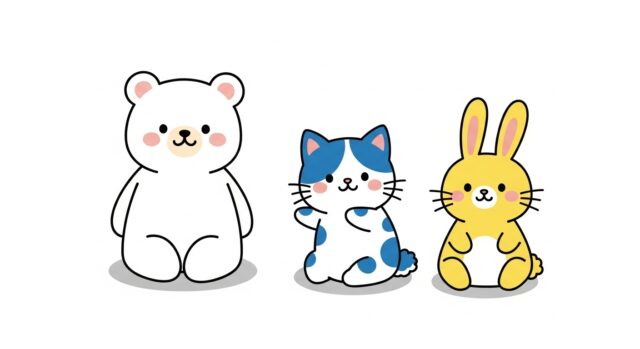













コメントを残す