「戦争を知らない世代」の責任
戦争が終わって80年が経ちました。
2025年の今、戦争を体験した人々は高齢となり、その記憶は少しずつ遠ざかっています。
私たちは、戦争を「過去のこと」として語るようになりました。
しかし、考えてみてください。
戦争とは、本当に過去のものなのでしょうか?
戦争の影響は、80年経った今も、私たちの社会に刻まれているのではないでしょうか?
戦争で家族を失った人々、戦後を生き抜いた人々、焼け野原から復興した日本──そのすべてが、今の私たちにつながっています。
そして、世界を見渡せば、戦争は今も終わることなく続いています。
戦争映画は、単なる娯楽ではありません。
それは、戦争を知る最後の手がかりであり、未来の平和を考えるための「証言」なのです。
今回は、戦後80年の今だからこそ観るべき、5本の戦争映画を紹介します。
これらの映画は、単なる歴史の物語ではなく、私たちが未来に何を残すべきかを問いかける作品です。
1.『黒い雨』──原爆の影を生きるということ

📌 監督: 今村昌平 (1989年)
📌 あらすじ:
1945年8月6日、広島。原爆が投下され、人々の生活は一瞬で変わった。爆心地近くで「黒い雨」を浴びた矢須子は、戦後も被爆者としての苦しみを抱えながら生きる。しかし、彼女の体には次第に被爆症状が現れ、結婚や将来の希望が断たれていく。
📌 特徴:
✔ 戦争の「その後」に焦点を当て、被爆者の現実を描く。
✔ 放射能被害、被爆者差別、戦後社会の不条理をリアルに表現。
✔ モノクロ映像が持つ圧倒的な臨場感と重み。
💬 ぐっちーのコメント:
広島の原爆資料館で「黒い雨」の証言を読んだとき、私は言葉を失いました。戦争が終わった瞬間、すべてが救われたわけではない。戦争は、その後も続いていたのです。
この映画は、戦争の「終わり」ではなく、その後に続く長い苦しみを描いています。
戦争とは、爆撃や戦闘だけではなく、その影が何十年も人々を苦しめるものなのだと、この映画が教えてくれました。
2.『火垂るの墓』──戦争が奪ったもの、戦争が遺したもの

📌 監督: 高畑勲 (1988年)
📌 あらすじ:
神戸の空襲で母を亡くした清太と節子の兄妹は、親戚に頼るが関係が上手くいかず冷たい扱いを受けたことにより、二人だけで生きようとする。しかし、戦争の現実はあまりにも厳しく、飢えと孤独に追い詰められていく。
📌 特徴:
✔ 戦争孤児の視点から「戦争の真実」を描く。
✔ 日本社会に潜む無関心と自己責任の風潮を鋭く映し出す。
✔ 「戦争は、銃を持った兵士だけのものではない」ことを痛感させる作品。
💬 ぐっちーのコメント:
「火垂るの墓」を観たとき、私は涙が止まりませんでした。
戦争は、ただ爆弾を落とすだけではない。戦争は、人々の心を冷たくし、誰かを見捨てることを正当化してしまう──そう、この映画は突きつけてきます。
3.『日本のいちばん長い日』──戦争を終わらせる苦悩

📌 監督: 岡本喜八 (1967年)
📌 あらすじ:
1945年8月15日、日本が終戦を迎えるまでの24時間。ポツダム宣言受諾をめぐる政治的駆け引き、クーデター未遂、昭和天皇の決断──後に「宮城事件」と呼ばれる出来事を通して、「戦争を終わらせる」ことに、どれほどの苦悩があったのかを描く。
📌 特徴:
✔ 「戦争を終わらせること」の難しさを描く。
✔ 終戦派と本土決戦派との対立による、極限の緊張感が続く。
✔ 日本の指導者たちが、いかにして終戦へと動いたかをリアルに描く。
💬 ぐっちーのコメント:
終戦か?本土決戦か?
ポツダム宣言を受諾し、これ以上の犠牲を防ごうとする終戦派と、あくまでも戦争継続に拘り、日本人としての誇りを優先する本土決戦派。双方の意見とも理解できるところがあり、自分がその立場だったらどんな選択をするのか?それを考えさせられました。
「戦争は終わった」のではなく、「終わらせた」のだ。
この映画を観たとき、その言葉の意味を痛感しました。
戦争は「終わる」ものではなく、「終わらせるもの」なのです。
4.『激動の昭和史 沖縄決戦』──地上戦に巻き込まれた人々の悲劇

📌 監督: 岡本喜八 (1971年)
📌 あらすじ:
太平洋戦争末期、日本本土決戦を目前に控えた沖縄。
日本軍は必死の防衛戦を繰り広げるが、圧倒的な物量を誇るアメリカ軍に次第に追い詰められていく。戦場は市街地へと拡大し、民間人すら戦闘に巻き込まれていく──軍と住民、両者が極限状態で迎えた「沖縄戦」の真実とは。
📌 特徴:
✔ 数少ない沖縄戦をテーマにした映画。
✔ 軍の視点・住民の視点の両方から、戦争の残酷さを描く。
✔ 実際の証言をもとに構築されたリアリティのある脚本。
💬 ぐっちーのコメント:
沖縄の平和祈念公園を訪れたとき、「沖縄戦」で亡くなった人々の名前が刻まれた「平和の礎(いしじ)」を目にしました。その数、20万人以上。
「沖縄戦は、日本本土を守るための時間稼ぎだった」という事実を知ったとき、私は胸が締めつけられました。戦争において、軍だけが戦うのではない。民間人もまた、戦場の中に巻き込まれていくのだと、この映画は教えてくれます。
沖縄戦を描いた映画は少なく、それゆえにこの作品の価値は計り知れません。ぜひ、観てほしい一作です。
5.『永遠の0』──「生きること」に執着した特攻隊員の真実

📌 監督: 山崎貴 (2013年)
📌 あらすじ:
戦後の日本。司法試験に落ち続け、自分の生き方に迷う青年・健太郎は、ある日、亡き祖父・宮部久蔵の過去を調べ始める。
宮部は、太平洋戦争中に特攻隊員として戦死した零戦パイロットだった。生前の彼を知る人々は、あるものは彼のことを「臆病者だった」と語り、またあるものは彼の人間性を評価した。なぜ彼は「生きること」に執着したのか? なぜ最終的に特攻隊に志願したのか?
戦争の記憶をたどる中で、健太郎は祖父の本当の思いに触れる──。
📌 特徴:
✔ 特攻隊員の「生きたかった」思いを描く。
✔ 迫力のある航空戦シーンと、リアルな零戦の映像表現。
✔ 家族の視点から、戦争の記憶を現代へとつなぐ物語。
💬 ぐっちーのコメント:
「特攻隊=死を覚悟した勇敢な戦士」と語られることが多いですが、彼らは本当に「死にたかった」のか?
この映画の宮部久蔵は、「生きて帰ることこそが最も大切だ」と訴える男でした。しかし、戦争の流れの中で、彼もまた「死」を選ばざるを得なくなる──この矛盾と葛藤が、心に深く刺さります。
私は鹿児島の知覧特攻平和会館を訪れたことがあります。そこには、特攻隊員たちが家族に宛てた遺書が展示されていました。どの手紙にも、「お母さん、ありがとう」「妹よ、元気で」「生きたかった」──そんな言葉が綴られていました。
「特攻隊=潔い死」などという単純なものではない。
その真実を、この映画は私たちに問いかけてきます。
📢 あなたの思う「平和」とは?
この記事で紹介した5本の映画は、どれも戦争を「単なる歴史」ではなく、「今も続く課題」として私たちに問いかけてきます。
あなたは、これらの映画の中でどの作品が最も印象に残りましたか?
また、戦争について考えるきっかけとなった出来事はありますか?
ぜひ、コメントであなたの考えを聞かせてください。
また、この記事をシェアして、より多くの人と「戦争の記憶」を語り合いましょう。
私たちは、80年後の未来に何を遺せるでしょうか?


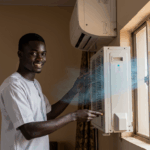









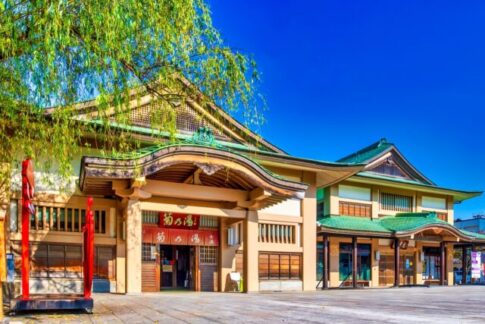





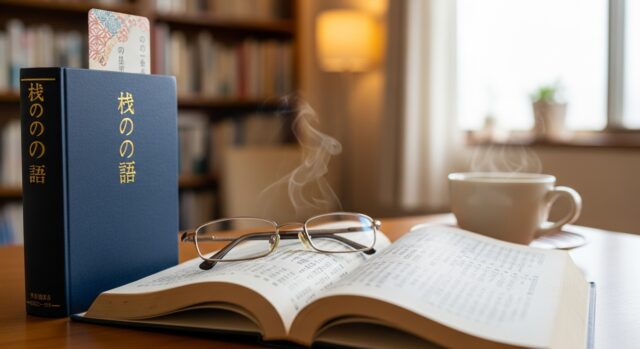



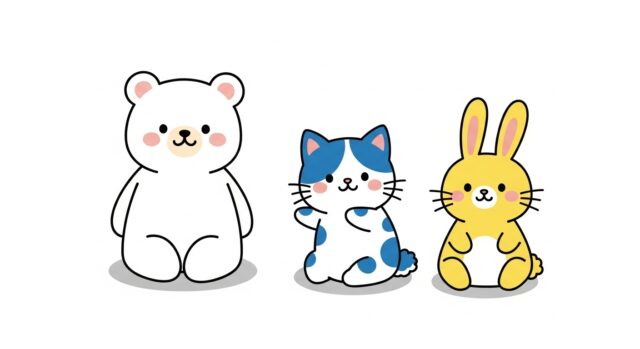













コメントを残す