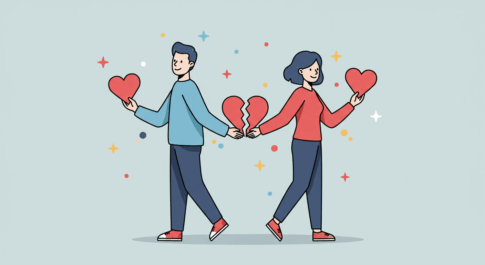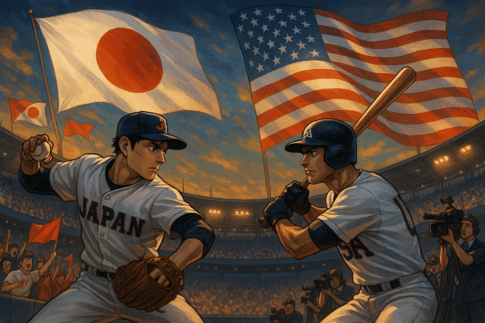🦕未知の動物から巨大生物に至るまで・日本における「怪獣」の由来と変貌🦕
Gracias、Es gucchi。 日本で誕生したゴジラをきっかけに、今や日本のみならずハリウッドまでに進出した「怪獣(Kaiju)」。ハリウッドで製作されている「モンスターバースシリーズ」の影響で、「タイタン(Titan)」と読んでいる海外の方もおられるのではないでしょうか? しかし、ゴジラが作られる以前の「怪獣」という呼び名の意味は、今とは全然違っていたのはご存じでしょうか?嘗て怪獣は「正体の知れない不思議な動物」という意味で、今のような「超常的な力を持った巨大生物」という意味ではなかったのです。それではどんな風に意味合いが変わったのでしょうか? 今回は、そんな知っているようで知らない「怪獣」の歴史をご紹介したいと思います。 中国大陸からやってきた「怪獣」 現在日本で使われている感じの殆どは、中国大陸がルーツ。当然、「怪獣」という文字も、同じく中国大陸がルーツでした。 中国の古文書である「山海経」は、戦国時代から秦朝・漢代(前4世紀 – 3世紀頃)にかけて書きあがったもので、中国大陸に伝わる霊獣や妖怪から、実際の動物を網羅した内容となっております。その中の山経5書の一つ『南山経』では、以下の文章が記述されています 又東三百八十里 曰猨翼之山 其中多怪獸 水多怪魚 多白玉 多蝮蟲 多怪蛇 多怪木 不可以上(東の380里を猿翼の山と呼び、その山中は怪獣が跋扈し、水には怪魚が数多あり、 真珠などの宝石に溢れ、マムシが這いまわり、大蛇や怪木に溢れている。 危険なので立ち入ってはならない) また、紀元前の文学者・司馬相如が記した「封禅文」には、この様な一文があります。 然后囿驺虞之珍群,徼麋鹿之怪兽(騶虞という珍しい動物を飼育し、四不像という奇妙な獣を狩った) ここで言う騶虞(すうぐ)や四不像というのは、古代中国では珍しい動物とされていますが、その彼らを「怪兽(奇妙な獣)」と呼んでいることが分かります。この様に、古代中国において「怪獣」という単語は「正体の知れない不思議な動物」という意味合いで使われ、現在で言う幻獣や妖怪を差す言葉だったのです。 江戸時代に登場した「怪獣」 それでは、日本で「怪獣」という単語が使われるようになったのは、いつ頃なのでしょうか? 実は意外と最近で、江戸時代辺りに 太田玩鴎という人物が記した「玩鴎先生詠物雑体百首」という書籍の中に、「怪獣」という単語が出てきたのが、日本における初出とされています。 También、上記の画像でもある「奥州会津怪獣絵図」という当時の瓦版には、東北地方で子供が失踪する事件が相次ぎ、その犯人である怪獣を仕留めたと記述され、その怪獣の姿かたちが描写されています。 También、同じく江戸時代には、現在の千葉県北部にある印旛沼で、江戸幕府の役人13名を殺害した怪獣の伝承が語り継がれています。地元民の創作ではないかという説もありますが、この当時から「怪獣」という単語が使用されていたことが分かります。 しかしながら、その当時の意味も「確認されていない生物・動物の類」というものであり、妖怪や魍魎とは少し違う意味合いで使われていました。 昭和初期・ゴジラ以前の「怪獣」 時代は江戸時代から、明治、大正、そして昭和へと移り変わりましたが、やはり依然として怪獣は「正体不明の不可思議な動物」という意味から逸脱していませんでした。 アメリカからやってきた「キング・コング」 そんな中、アメリカから「キング・コング」という革命的とも言うべき特撮映画が上陸してきました。巨大類人猿のキングコングが、ジャングルやニューヨークを舞台に大暴れする内容のこの映画は、日本国内で大ヒットを遂げました。後に、ゴジラを製作することになる円谷英二も、この映画に影響されるなど、後の特撮に多大な影響を与えました。 しかしながら、この時の呼称は「怪物」「巨獣」「巨猿」などが主流で、「怪獣」という単語はマイナーな方でした。 未確認生物の呼び名だった「怪獣」 では、当時から「怪獣」に該当し、そう呼ばれていたものとは一体何でしょうか? 実は、「ネス湖のネッシー」や「ヒマラヤの雪男」など、現在日本では「UMA(Unidentified Mysterious Animal)」と呼ばれ、海外では「Cryptid 」と呼ばれている未確認生物たちを差していたのです。姿かたちがハッキリしない彼らは、まさに「正体不明の不可思議な動物」そのものでした。 意外なことに、日本での彼らの紹介は古く、遅くとも明治時代頃からでした。そもそもネッシーは中世の時代から目撃談のある存在で、彼らが怪獣とされていたのは、目撃されているにも関わらず、一度も捕獲されたことが無い為、存在が確定出来なかったという点にあります。 También、当時の文豪・太宰治の小説にも、この様な一文があります。 私の下宿のすぐ裏が、小さい公園で、亀の子に似た怪獣が、天に向って一筋高く水を吹上げ、その噴水のまわりは池で、東洋の金魚も泳いでいる。 女の決闘 -太宰治- 1940年(昭和15年) この文章では、街中で見かけた見慣れない動物でさえも「怪獣」と呼称しており、ゴジラ以前の怪獣達は「見慣れない奇妙な動物」という意味から脱却しきれていませんでした。 「怪獣」に大革命をもたらしたゴジラ そんな「怪獣」という単語に転機が訪れたのは、皆さんご存じの「ゴジラ」の登場でした 当時のポスターには「水爆大怪獣映画」の一文が添えられており、これが「怪獣」が現在の意味へと変化するきっかけとなりました。pero、意外なことに検討用の台本では「怪獣」という単語は存在せず、「巨獣」や「恐竜の生き残り」と表記されるだけでした。Bueno entonces、何故この時「怪獣」という単語が使われたのでしょうか?実は、アメリカから上陸してきた、ある特撮映画がきっかけだったのです。 その映画こそが「原子怪獣現る(The Beast from 20,000 Fathoms)」でした。原水爆で目覚めた太古の恐竜が、ニューヨークで暴れまわるという内容は、ゴジラにも少なからず影響を与えていました。Y、奇しくも両作はほぼ同時期に封切られることになり、日米対決と話題にもなったのです。 東宝部としても、何としてもゴジラを売り出したいと、負けじと大々的な宣伝を繰り返しており、ポスターにある「水爆大怪獣映画」も、宣伝部が付けたものでした。おそらく、当時の東宝も「あっちが原子怪獣なら、こっちは水爆大怪獣だ!」と、売り言葉に買い言葉といった対抗心から命名したのでしょう。 何はともあれ、これによりマイナーだった「怪獣」は、「未確認生物」に加え「ゴジラ」という新しい意味を与えられ、一般へと流布されるようになったのです。 恐竜ではないリアリティを与えられた「怪獣」 また、劇中でのゴジラは、怪獣本来の意味でもある「正体不明の不可思議な生物」を体現した存在でもありました。 というのも、劇中ゴジラは「海棲爬虫類から陸上獣類へ進化する過程の中間生物」という現実では存在しえない、全く未知の生物として解説されており、「恐竜」でさえない存在なのです。結局、劇中ではその正体が不明なまま映画が終わってしまい、ゴジラは文字通りの正体不明の生き物「怪獣」だったのです。 ゴジラ以前にも、「キング・コング」のコングや、「ロスト・ワールド」のブロントザウルスといった怪獣的な振る舞いをするモンスターは居ましたが。ゴジラが決定的に違っていたのは、種別がハッキリしない正体不明の動物であったことでした。それはまさに、かつて存在が信じられながらも正体がハッキリしなかった、ネッシーや雪男のような「何処かにいるかもしれない」というリアリティを与えるものでした。 こうしてゴジラは、「恐竜」ではないからこその絶妙なリアリティを帯びた存在として、独特の存在感を観客に与えたのです。 見世物として銀幕を席巻した「怪獣」...