日本で人気の高い中華料理は様々有りますが、特に独自の食文化と味を構築したラーメンは
今や日本を代表する国民食です。
ラーメンの歴史を説明すると日本に中華料理が提供される様になってからであり、日本での中華料理の普及とラーメンはリンクしている事から、日本初の中華料理のルーツを追う事がラーメン誕生の歴史に結びつきます。

日本で初めて中華料理が提供される様になった記録や伝承がいくつかありますが、資料も少なく、明確に「これが日本初」と定義することは難しいです。
ただし明確な経緯を整理し考察していくと、日本に中華料理が紹介され、普及する過程については以下のような歴史があります。
長崎と中国の交流

江戸時代に長崎は、鎖国下でも中国との貿易が行われた主要な窓口でした。この時期に長崎の唐人屋敷跡があった、広馬場町に中華料理店四海楼が1899年明治32年に創業しました。
創業者は中国清朝時代の福建省出身者、陳平順で、華僑や中国人留学生に提供した料理が長崎ちゃんぽんや皿うどんとなります。
旨くてボリュームが有り、栄養価が高く安価な料金で提供する為に、鶏ガラと豚骨のスープを使い、長崎でとれる山海の幸をふんだんに使った麺料理を考案しました。
当初はメニューにない料理で「支那饂飩」とよばれていましたが、当時の長崎華僑が交わしていた福建語の挨拶言葉(シャポン)または(ご飯を食べるという意味)のセッポンから「ちゃんぽん」と呼ばれるようになったという説があります。
「皿うどん」もちゃんぽんから派生した料理で、同じく四海樓の創業者である陳平順が考案しました。
ちゃんぽん麺を一度焼いて具材と一緒に炒め、少なめのスープを加えて麺にしみ込ませる調理方法で、平皿に盛られた汁なしの麺料理が、見た目そのままに「皿うどん」と名前がついたそうです。
関東方面の中華そば

関東方面ではラーメンに似た中華そばを提供していたのが、東京浅草で明治43年創業した來々軒で創業者の尾崎貫一氏は横浜税関に務め52歳で退職した異例の経歴の持ち主で、退職金で横浜中華街の広東省出身の中国人12名を招き、浅草公園に来々軒を開業します。
創業当初は中華そば・ワンタン・シューマイの三種類のみのメニューで、当時珍しい中華そばをメニューにした尾崎氏は若いころ中華街近くの伊勢佐木町に住み中華街で細切りの豚肉を入れた「豚蕎麦・ラウメン」を食べていたそうです。その味をアレンジし、中華そばを提供し、日本初のラーメンブームを起こしました。
1922年(大正11年):初代・貫一の死去により長男の尾崎新一氏が経営を引き継ぎます。
1927年(昭和2年):夫・新一の死去により妻・あさが経営を引き継ぐ。この時、11歳であった長男一郎(後の三代目)の子育てもあり、家業を維持するため、堀田久助(義兄)及び高橋武雄(義弟)の補佐により運営します。
1935年(昭和10年):浅草から独立し上野で来々軒を創業しますが、戦争が始まり、1994年(昭和19年)浅草店の三人の息子達が戦地へ赴いたので、一度浅草店を閉店させます。
1945年(昭和20年):戦後、戦地から復員した三代目一郎氏が昭和20年に東京駅八重洲口に新たに来々軒を出店させました。
来々軒は、1976年(昭和51年)に閉店するまで、醤油味のスープに中華麺を合わせた「中華そば」を提供し、日本国内で中華麺を使う料理、ラーメンの認知を広げました。正月等の繁忙期には1日2500食~3000食も提供し大繁盛したそうです。しかし、一郎氏には血縁の後継者がおらず、閉店。その後、来々軒で修業し、味を継承した弟子達がそれぞれ店を持ち、千葉市の進来軒や郡山市のトクちゃんを開店させ、来々軒でラーメンの他にも人気だった天津飯や中華丼の発祥の味も受け継いでいます。
[祐天寺 来々軒]と[泰雅]
![[祐天寺 来々軒]と[泰雅]](https://kawaraban.jp/wp-content/uploads/2025/05/image_fx-44.jpg)
直弟子の中に、傅興雷(フコウライ)という人物が後に浅草本店の料理長となる。その後、1933年に独立したのが[祐天寺 来々軒(当時は大森)]。その孫にあたる3代目の長江さんが独立して開いたのが学芸大学にある[泰雅]です。
2020年には創業者の子孫の協力を得て[祐天寺 来々軒]が「浅草来々軒」として新横浜ラーメン博物館にオープンしました。
「浅草 來々軒」

「浅草 來々軒」はこのように近親者や弟子達によって味が継承されていった経緯があり、新横浜ラーメン博物館で、浅草来々軒の味の再現を試みた際に、断片的なものや不明な点もある為、100%当時の味を再現するというものではありません。しかしながら不明な点は当時の裏付けのある資料や食事情、時代背景から推測をし、末裔の承認を受けたもので再現しました。
近親者や弟子達に取材を行った結果、かなり本格的な現在のラーメンに近い原型まで完成されていた様で、証言に伴い再現した当時のレシピは現在の人気ラーメン店にもひけを取らない味に仕上がりました。
国産の豚、鶏、野菜に、昭和初期頃から加えられた煮干も使用したスープをベースに、麺に使用する小麦は、明治まで遡り、当時の遺伝子を持つ後継品種「さとのそら」を使用。創業当時の「青竹打ち」と昭和10年以降の「機械製麺」2種類で、食感の違いを楽しめる様です。
メンマは、台湾産の乾燥メンマを1週間かけて水で戻し、味付け。焼豚は、味をなじませてから、直火の吊るし焼きにしています。その手法が昔ながらの手間暇かけた伝統で中国料理をベースに、日本人の口に合うようにアレンジされた料理を提供した現在のラーメンの原型が新横浜ラーメン博物館で楽しめるそうです。
まとめ

ラーメンは昔ながらという言葉がついていても日々進化して、実のところは当時の味なんてどこにも残っていないのかもしれません。それでも、親族やお弟子さんの力を得て、良いものを残していこうとするその心意気などが進化として味に出ているのかもしれません。
新横浜ラーメン博物館ではこのほかにも様々なお店が出展され、不定期に入れ替わっているようなのでぜひ遊びに行って、どこのラーメンが美味しかったか、コメントで教えてください。
シェアも大歓迎です!私も今日のお昼はラーメンになりそうです。


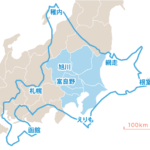













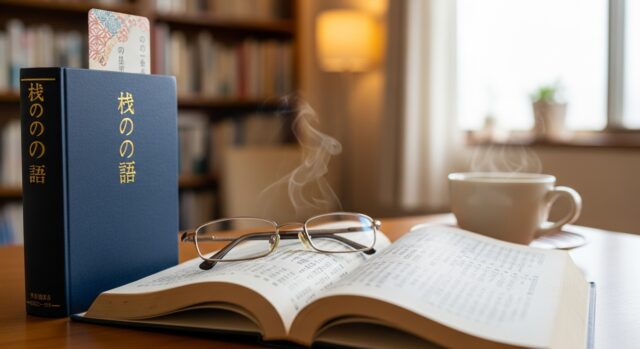



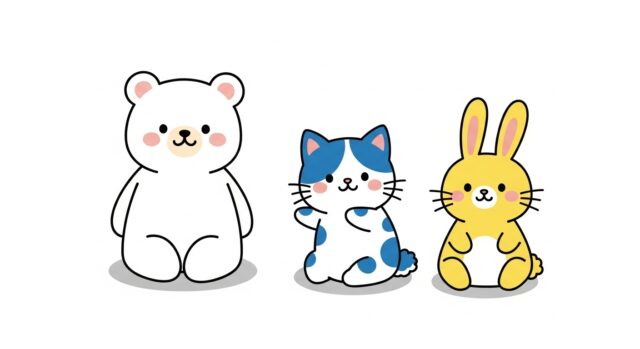













コメントを残す